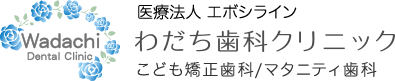小児歯科

歯科医院において、大人の歯を診察する「一般歯科」とは異なり、「小児歯科」という専門診療科目が存在します。
名前からも分かる通り、小児歯科は主に子供の歯に特化した診療を行います。このように大人と子供の診療を分けて行うのは、それぞれの治療方針が異なるからです。
子供の歯科デビューは、乳歯が生え始める生後6ヵ月頃からが最適です。
多くの地域では、1歳半になると初めての歯科健診が行われますが、歯が生え始める段階から虫歯のリスクが存在します。
さらに、歯が生え始めた時期と生え揃った時期では、ブラッシングや注意すべきポイントが異なるため、早い段階から歯医者を訪れ、子供の成長に合った予防方法を学ぶことが重要です。
小児の歯科治療において心がけるべき3つのポイント
子供が元気な午前中や早い時間に治療を受けましょう。
子供は昼過ぎから夕方にかけて疲れやすく、その時間帯に治療を受けると機嫌が悪くなる可能性が高いです。
治療を受ける際は、子供が元気な午前中や早い時間を選びましょう。
治療を終えた後はたくさん褒めてあげましょう。
歯科治療は子供にとって緊張や恐怖を感じることがあり、痛みや不快な感覚も伴います。
治療後は、子供が頑張ったことをたくさん褒めて励ましましょう。
治療前はできるだけリラックスして待機しましょう。
治療を受ける前に子供がリラックスした状態でいることは重要です。
待合室で本を読んだり、おもちゃで遊んだりして緊張を和らげ、子供の不安を軽減しましょう。
歯医者を好きになってもらえるように
子供たちが歯医者を好きになるようにするために、わだち歯科クリニックでは以下の4つの取り組みを行っています。
子供たちの緊張をほぐす

初めて来院する子供たちに対して、痛みがひどくない限り、すぐに治療を開始しません。
子供たちにとって、知らない大人に歯を削られる治療は恐怖を感じることが多いです。
そのため、当院では子供たちとゆっくりとコミュニケーションを取りながら、歯科治療に慣れさせる取り組みを行っています。
お子さんにも治療内容を説明する

治療内容を子供たちに理解しやすく説明する努力をしています。
虫歯の進行や治療のプロセスについて、子供たちが理解しやすいように説明することで、不安を軽減しようとしています。
親御さんにも同席していただく

子供の治療時には、親御さんも同席していただくようお願いしています。
これにより、子供たちが適切な治療を受けていることが親御さんにも確認され、治療や予防に関する知識を共有できる機会を提供しています。
「咬合誘導(アゴの発育)」の推進

子供の歯は成長と歯の生え変わりによって絶えず変化しています。
現在歯並びに問題がなくても、将来的に悪化する可能性があるため、「咬合誘導」を提案しています。
これは、子供のあごの成長に合わせて歯の位置を調整し、歯並びを整える方法です。
わだち歯科クリニックの小児歯科では、子供たちの歯を虫歯にならないように予防し、お母さんたちの子育てをサポートすることを最優先に考えています。
この地域に住む多くの子供たちが当院を受診しており、丹羽郡、江南市、犬山市で小児歯科をお探しの方は、ぜひ当院にご相談ください。
お子様の健康な笑顔を守るお手伝いをさせていただきます。